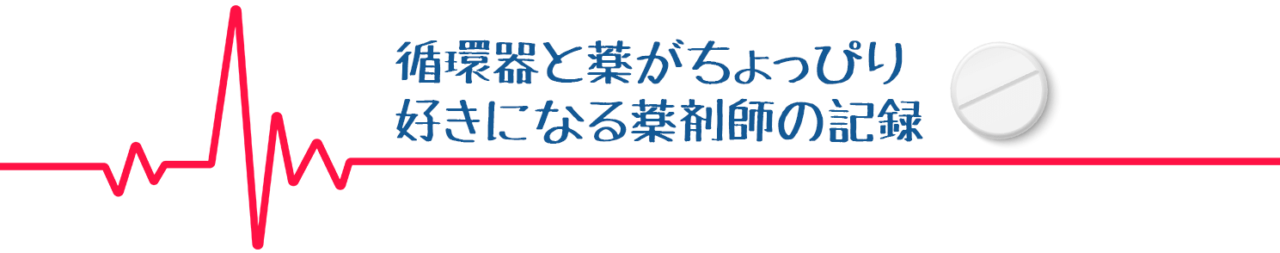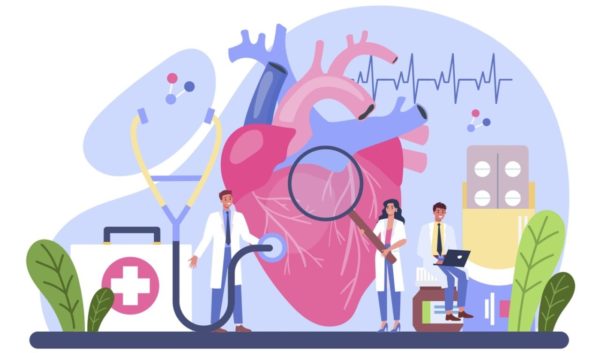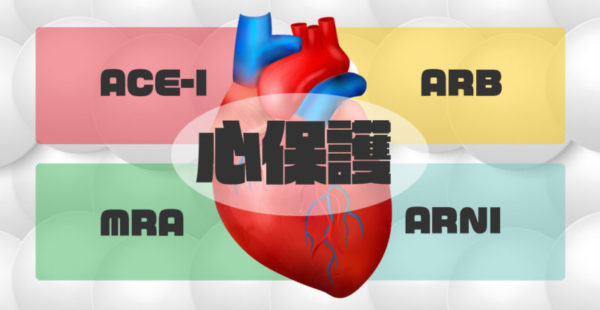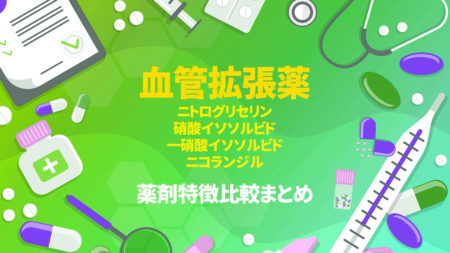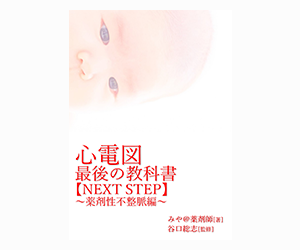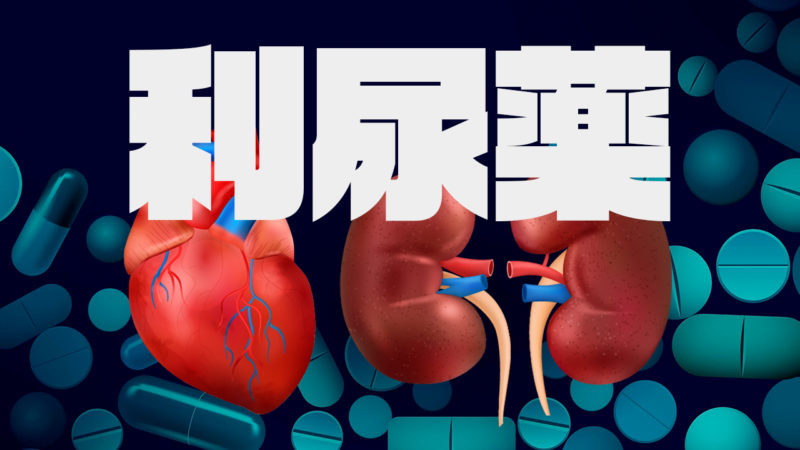
心不全の薬物療法に用いられる薬の作用は、血圧・体重・尿量などの指標で効果が分かりやすい目に見える作用と、心臓を護る・心臓の負担を減らすなど予後を改善するような効果が分かりにくい目に見えにくい作用があるとコチラの記事で記載しました。
また、心不全を重い荷物を運ぶ状態をイメージとすると、利尿薬(利尿作用を持つSGLT-2阻害薬含む)は運ぶ荷物を減らして疲れないようにしようというイメージとお伝えしました。

さて、利尿薬は心不全の体液管理を目的として使用されます。つまり、荷物とは余計な水分のことです。余計な水分を体外に尿として出してあげることで、心不全症状が出ないようにしているのです。
しかし利尿薬といってもループ利尿薬、チアジド系利尿薬、カリウム保持性利尿薬、バソプレシンV2受容体拮抗薬などの種類があります。また、糖尿病薬として発売されたSGLT-2阻害薬も利尿作用があり、心不全に対して予後を改善するといった報告も増えてきました。この記事ではこれらの薬剤の違いについてイメージがつかめるようにまとめていきたいと思います。
Contents
利尿薬
利尿薬は前負荷を改善する薬剤です。前負荷を改善するためには余分な水分を取り除くか、血管を拡張して容器を大きくするかです。利尿薬は余分な水分を取り除くことで前負荷を改善します。(詳細はコチラの記事参照)

利尿薬全般の目に見える作用、注意する副作用についてです。(心臓を護る・心臓の負担を減らすなど予後を改善するような効果が分かりにくい目に見えにくい作用については該当する薬剤のところで記載いたします。)
- 目に見える作用:尿量増加、血圧低下
- 注意する副作用:各薬剤の項目参照
利尿薬は体内の過剰な水分(うっ血)を腎臓から尿として体外に排出するために用いられています。
うっ血を取り除き、うっ血に伴う自覚症状を改善させることが目的です。そして体液をコントロールしてうっ血に伴う自覚症状を予防することが目的です。
全身循環より左心不全、右心不全ではどこにうっ血するかが分かります。

下のように左心不全では肺にうっ血し、右心不全では全身にうっ血します。

利尿薬とは、うっ血を取り除く・予防することで、心不全の自覚症状を取り除く・症状が出ないように予防する薬なのです。
また、利尿薬はナトリウムイオン(Na+)やカリウムイオン(K+)などの電解質に影響を与えます。特にK+は高カリウム血症、低カリウム血症となると命の危険があるため、電解質をチェックする必要があるのです。
各利尿薬の作用部位を図示します。

- ループ利尿薬:ヘンレループ上行脚のNa+K+2Cl-共輸送体に作用して、電解質(Na+、K+、Cl-)の再吸収をブロックする。
- チアジド系利尿薬:遠位尿細管のNa+/Cl-共輸送体を阻害して、Na+の再吸収をブロックする。
- カリウム保持性利尿薬:集合管のアルドステロン受容体を遮断して、Na+の体内への再吸収、K+の尿への排泄をブロックする。
- バソプレシンV2受容体拮抗薬:集合管のバソプレシンV2受容体に拮抗して、水(H2O)の再吸収をブロックする。
通常であれば、各薬剤の作用部位では、電解質や水が体内に再吸収されます。(Na+は水をたくわえる電解質になりますので再吸収されるのと一緒に上記図の→のように水も再吸収されます。)薬を使うことで各作用部位での水分の再吸収をブロック(上記図の×)することで、尿量を増やします。
ループ利尿薬、チアジド系利尿薬、カリウム保持性利尿薬を使用するとNa+の再吸収を防ぎます。Na+は水をたくわえる電解質になりますので、『Na+の再吸収を防ぐ=尿量が増える』ということになります。作用機序をイメージすると利尿薬の併用は、単剤で使用するよりも利尿作用が高まることは理解しやすいのではないでしょうか。
では各利尿薬の特徴ついて見ていきましょう。
ループ利尿薬
ループ利尿薬はヘンレループ上行脚のNa+K+2Cl-共輸送体に作用して、電解質(Na+、K+、Cl-)の再吸収をブロックします。
- 目に見える作用:尿量増加、血圧低下
- 注意する副作用:低カリウム血症
- 薬:先発医薬品名(成分名)
・ラシックス®(フロセミド)
・ダイアート®(アゾセミド)
・ルプラック®(トラセミド)
一般的に利尿薬というと、頭に思い浮かべるのがループ利尿薬ではないでしょうか。
ループ利尿薬の利尿効果が最も強いです。(理由は記事内の『バソプレシンV2受容体拮抗薬はなぜ利尿薬の併用が必要なのか?』の部分に一緒に記載しています。)
フロセミドの内服が効きにくい、腸管浮腫って聞いたことありますか?
腸管浮腫とは文字通り腸管の浮腫ですが、浮腫んでいる結果、内服薬の腸管からの吸収率が低下します。薬が体内に吸収されにくい状態ということです。
心不全急性期や重症例では腸管浮腫によって内服薬を増やしても薬が吸収されないため尿量が増えないケースがあります。
こういったケースでは血管内に直接投与、つまり静脈注射してあげれば薬が吸収されないといった問題は解決できます。
参考までにフロセミドを経口で投与した場合その吸収率は約50%なので、同程度の効果を望むのであれば静脈注射20 mg≒経口40 mgとなります。
よくあるフロセミド20 mg静脈投与から、フロセミド20 mg内服への切り替えは、同じ投与量のように思えますが、薬物血中濃度からみると減量になります。
チアジド系利尿薬
チアジド系利尿薬は遠位尿細管のNa+/Cl-共輸送体を阻害して、Na+の再吸収をブロックします。
- 目に見える作用:尿量増加、血圧低下
- 注意する副作用:低カリウム血症
- 薬:先発医薬品名(成分名)
・先発医薬品は販売中止(ヒドロクロロチアジド)
・フルイトラン®(トリクロルメチアジド)
など
利尿作用よりは降圧目的に使用されることの方が多いです。(まずはループ利尿薬が選択されることが多いため)
カルシウム受容体拮抗薬やACE-I/ARBなど他の降圧剤を使用していても血圧が高い方に少量で投与されます。
カリウム保持性利尿薬
カリウム保持性利尿薬は集合管のアルドステロン受容体を遮断して、Na+の体内への再吸収、K+の尿への排泄をブロックします。
- 目に見える作用:尿量増加、血圧低下
- 目に見えにくい作用:心保護作用
- 注意する副作用:高カリウム血症、女性化乳房(スピロノラクトン)
- 薬:先発医薬品名(成分名)
・アルダクトン®A(スピロノラクトン)
・セララ®(エプレレノン)
※ミネブロ®(エサキセレノン)は心不全の適応なし
ループ利尿薬やチアジド系利尿薬より、利尿作用は乏しいです。この薬のメリットはカリウムの尿排泄を抑えるところです。ループ利尿薬やチアジド系利尿薬は、カリウムを尿に排泄します。それに対し、カリウム保持性利尿薬はその名前のとおり、カリウムを保持(尿への排泄を抑える)します。低カリウム血症の抑制、カリウムの補正をするために、他の利尿薬と併用して用いられることが多いです。
カリウム保持性利尿薬はミネラルコルチコイド受容体拮抗薬とも言われ、目に見えにくい作用として心臓を保護する作用もあります。
スピロノラクトンの特徴的な副作用に女性化乳房があります。認められる場合はエプレレノンへの変更を検討します。
高カリウム血症のリスクがあるため、腎機能低下時の投与に注意が必要です。
重度の腎機能障害(クレアチニンクリアランス30mL/分未満)患者に対してスピロノラクトンは投与可能(※注意は必要)ですが、エプレレノンでは投与禁忌に該当します。
バソプレシンV2受容体拮抗薬
バソプレシンV2受容体拮抗薬は集合管のバソプレシンV2受容体に拮抗して、水(H2O)の再吸収をブロックします。水利尿薬とも言われ、電解質に影響を与えにくい利尿薬です。他の利尿薬と併用して使用します。
- 目に見える作用:尿量増加、血圧低下
- 注意する副作用:口渇、急激なナトリウムの上昇、肝機能障害
- 薬:先発医薬品名(成分名)
・サムスカ®(トルバプタン)
利尿薬の中でも特に口渇が発現しやすいので、口渇を感じにくい方や訴えることのできない方への投与は要注意です。
また、水分制限が緩和されることがあります。心不全患者さんに水分制限についてどのように言われているか確認しましょう。
バソプレシンV2受容体拮抗薬はなぜ利尿薬の併用が必要なのか?
バソプレシンV2受容体拮抗薬の効能効果は『ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留』となっています。
腎臓が一日にろ過する血液の量(原尿)は約150Lといわれており、そのうち約99%が再吸収されます。なので、実際の尿量は約1.5Lということになります。
どこでどのくらい再吸収されるのかですが、原尿は集合管に届くまでに95%以上の水分が体内に再吸収されます。
バソプレシンV2受容体拮抗薬を単剤で使用した場合、95%以上は体内に水分が再吸収された状態です。つまり、バソプレシンV2受容体拮抗薬を単独で使用しても効果は低いです。

集合管より上流の作用機序の薬剤(ループ利尿薬、チアジド系利尿薬など)を使用することで、集合管まで届く尿量を増やすことで、バソプレシンV2受容体拮抗薬の効果を引き出します。これが、バソプレシンV2受容体拮抗薬が他の利尿薬との併用が必要な理由です。
また、なぜループ利尿薬の利尿効果が最も高いのかについても同様です。上流で作用することで下流まで届く尿量が増えるからです。
このように作用機序を理解すると、なぜという疑問を理解することができます。単純にループ利尿薬を増量するよりも、カリウム保持性利尿薬やバソプレシンV2受容体拮抗薬を併用するほうが複数の作用機序をブロックすることで利尿作用が強くなりそうというイメージもしやすくなったのではないでしょうか。
SGLT-2阻害薬
- 目に見える作用:血糖低下、尿量増加
- 目に見えにくい作用:心血管保護(明確な機序は不明)
- 注意する副作用:低血糖
- 薬:先発医薬品名(成分名)
・フォシーガ®(ダパグリフロジン)
・ジャディアンス®(エンパグリフロジン)
・カナグル®(カナグリフロジン)
・スーグラ®(イプラグリフロジン)
・ルセフィ®(ルセオグリフロジン)
・デベルザ®(トホグリフロジン)
※すべてに心不全の適応があるわけではありません。
SGLT-2阻害薬は糖尿病の治療薬として登場しましたが、尿量増加や心血管保護作用があるため、心不全に対して良い結果が報告されたSGLT-2阻害薬は慢性心不全患者に使用されるようになってきています。
2021年10月28日調査時点では慢性心不全に適応が通っている薬剤はダパグリフロジンのみです。エンパグリフロジンは10月27日に慢性心不全に対する適応拡大の申請を厚生労働省に行ったとプレスリリースされていました。
さて、糖尿病薬として発売されたSGLT-2阻害薬でなぜ尿量が増えるのか?
SGLT-2は、腎臓の近位尿細管に存在し、尿中のほとんどのグルコースを再吸収しています。SGLT-2を阻害することで、過剰な血中の糖を尿から排泄して血糖値を下げる薬剤です。
普通であれば、糖尿病の場合、尿検査で尿糖陽性となりますが、SGLT-2阻害薬使用患者さんの尿糖が陽性だからといって糖尿病というわけではありません。
SGLT(sodium glucose co-transporter)とはナトリウム・グルコース共役輸送体のことです。
SGLT-2は糖(図:Glu)とNa+を再吸収しますが、SGLT-2阻害薬は再吸収を阻害します。Na+と一緒に水分も再吸収されますので、SGLT-2を阻害することでNa+と水分の吸収が抑えられ、尿量が増えるのです。

また、副作用に低血糖と記載していますが、SGLT-2阻害薬単独では起きにくいです。他の糖尿病薬と併用する際は注意してください。
α型ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド
- 目に見える作用:心不全自覚症状の改善、血圧低下
- 目に見えにくい作用:心保護作用
- 注意する副作用:血圧低下
- 薬:先発医薬品名(成分名)
・ハンプ®(カルペリチド) - 持続点滴

α型ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチドは心不全急性期に持続点滴で使用可能な薬剤で、血管拡張作用と利尿作用(腎血流量、糸球体濾過率を増加させる)を持つ薬剤です。また、心肥大抑制・線維化抑制などの心保護作用も示します。
まとめ
- 利尿薬は前負荷を改善する薬剤です。
- 利尿薬は体内の余分な水分を体外に出す薬で、水分という運ぶ荷物を減らすことで心臓にかかる負担を減らすイメージの薬です。

- 各利尿薬の作用機序を理解しましょう。
- ループ利尿薬:ヘンレループ上行脚のNa+K+2Cl-共輸送体に作用して、電解質(Na+、K+、Cl-)の再吸収をブロックする。
- チアジド系利尿薬:遠位尿細管のNa+/Cl-共輸送体を阻害して、Na+の再吸収をブロックする。
- カリウム保持性利尿薬:集合管のアルドステロン受容体を遮断して、Na+の体内への再吸収、K+の尿への排泄をブロックする。
- バソプレシンV2受容体拮抗薬:集合管のバソプレシンV2受容体に拮抗して、水(H2O)の再吸収をブロックする。
- SGLT-2阻害薬:糖(グルコース)とNa+の再吸収をブロックする。(心不全の適応は一部の薬剤のみ)
- α型ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド:血管拡張作用により腎血流量の増加→糸球体濾過率の増加→尿量の増加(下記図には記載なし)

- その他のポイント
- 腸管浮腫の場合は内服薬が吸収されにくく利尿効果が得られにくいため、点滴投与を検討しましょう。
- トルバプタンは単独投与ではなく、他の利尿剤と併用しましょう。
________
このブログが書籍になりました。『心不全×くすり ゼロから楽しく学ぶ3step』

こんなコメントもいただいています。
挫折せず一気読み出来ました!
中でもコラムが気に入りました。
心不全について様々な参考書を購入してきましたが、今までで一番イメージがつかみやすく、読みやすかったです。