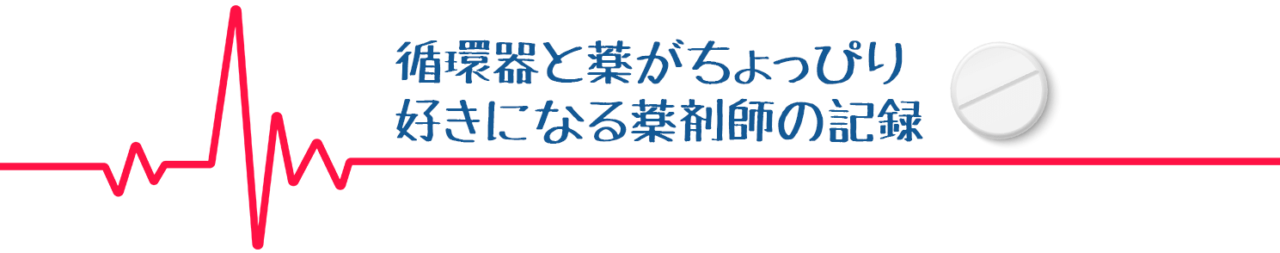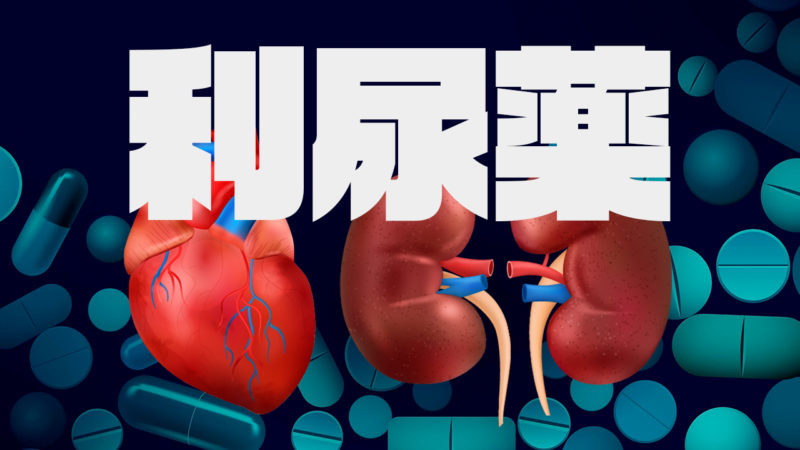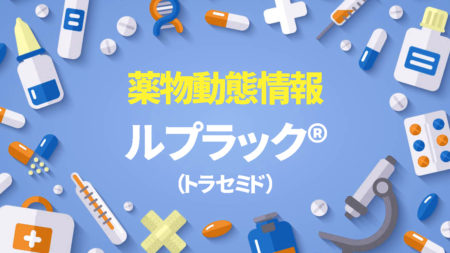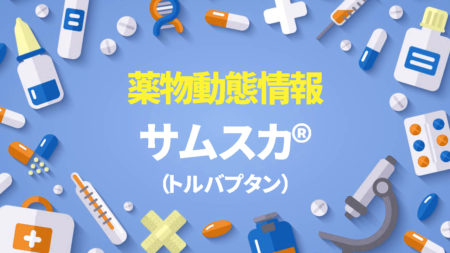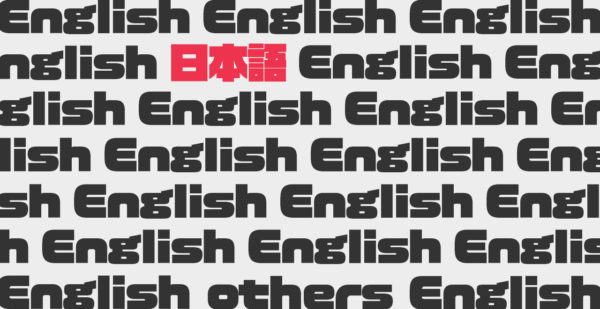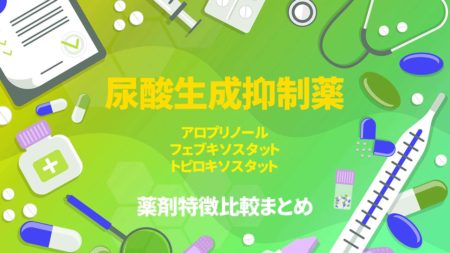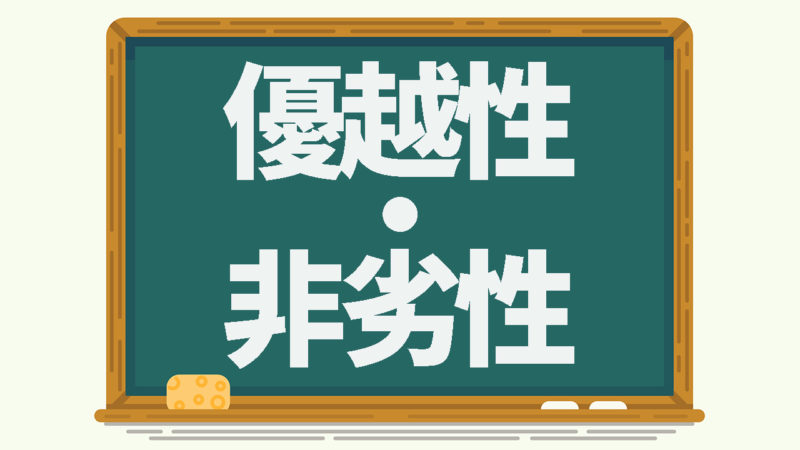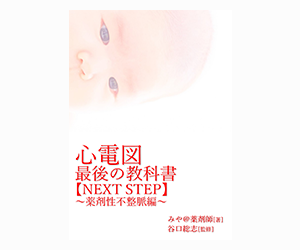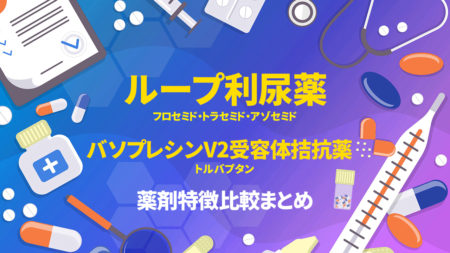
ループ利尿薬とトルバプタンの薬物動態情報をまとめました。
カリウム保持性利尿薬(ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬)については別でまとめる予定です。
また、利尿薬の作用機序についてはコチラの記事にまとめています。
では、ループ利尿薬とトルバプタンについてみていきましょう。
動画でサクッと聞き流し(1.5倍速推奨)[10:18]
Contents
ループ利尿薬・トルバプタン薬物動態情報まとめ

個々の医薬品についてはコチラの記事たちをご覧ください。
ループ利尿薬
ループ利尿薬は近医尿細管(ヘンレループ上行脚)のNa+K+2Cl–共輸送体に作用して、電解質(Na+、K+、Cl–)の再吸収をブロックして作用を示す利尿薬です。
内服薬としてフロセミド、トラセミド、アゾセミドがあります。
また、フロセミドは注射剤もあります。フロセミドのバイオアベイラビリティが51%のため、経口投与時に約半分が吸収されないということになります。そのため、フロセミドは静脈注射20 mg≒経口40 mgとなります。腸管浮腫など腸管から吸収されにくい場合ではフロセミド静脈注射が用いられます。
無尿の人にループ利尿薬を投与しても効果はありません。
タンパク結合率
血漿中遊離形率(fuP)はフロセミド、トラセミド、アゾセミドともに0.2%未満と低く、タンパク結合依存型の薬剤といえます。
ループ利尿薬はタンパク結合した、つまりアルブミンと結合した状態で、腎糸球体を通過し近医尿細管に作用し効果を示します。
アルブミン投与後のフロセミド静脈投与という指示を見ることもあると思いますが、これは利尿効果を高めるためにフロセミドに結合するアルブミンを補充してあげているということです。
作用時間
フロセミド < トラセミド < アゾセミド
フロセミドは短時間作用型ループ利尿薬です。それに対し、トラセミド、アゾセミドは長時間作用型のループ利尿薬です。作用時間が一番長いループ利尿薬はアゾセミドになります。また、トラセミドは単剤で抗アルドステロン作用があります。
予後に与える影響
短時間作用型ループ利尿薬(フロセミド)の長期投与によりレニン・アンジオテンシン・アルドステロン(RAA)系が賦活化されて予後を悪化させることがあります。
そこで長時間作用型のループ利尿薬という選択肢です。フロセミドと比較してアゾセミドは心血管死または心不全悪化による入院の改善が期待できるという報告1)もあります。また、ループ利尿薬の投与量が多いほど、心不全患者は死亡率のリスクが高いという報告2)もあります。
そのため、ループ利尿薬を高用量投与するのではなく、トルバプタンやミネラルコルチコイド受容体拮抗薬など他剤を併用します。(高度腎機能低下患者では、アルブミンが低下しているために、高用量必要とする場合があります。)
低カリウム血症
ループ利尿薬はカリウムを排泄するため低カリウム血症に注意が必要です。
抗アルドステロン作用はカリウム保持性がありますので、抗アルドステロン作用を持つトラセミドは抗アルドステロン作用を持たないフロセミド、アゾセミドと比べて低カリウム血症のリスクは低い可能性があります。(しかし注意は必要です。)
ループ利尿薬の選択(個人的見解)
急性期は短時間作用型ループ利尿薬のフロセミド、腸管浮腫の可能性がある場合は静脈投与を選択します。
体液コントロールができてきたら、必要に応じて長時間作用型ループ利尿薬に変更を検討すると思います。心不全の場合はミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MRA)も併用するとおもいますので、トラセミド、アゾセミドどちらでも良いと思います。
短時間作用型ループ利尿薬と長時間作用型ループ利尿薬を併用するケースもあると思います。例えば、朝食後をフロセミド、昼食後をトラセミドまたはアゾセミドといった感じです。
どの利尿薬が選択されていたとしても重要なのは、体重が増えないことです。利尿量が減ると過剰な水分は体重増加として現れます。そのため退院後は日々の体重測定が重要で、目標体重から+2~3㎏以上増えているようであれば、自覚症状がなくても早期受診するように指導しています。
トルバプタン
トルバプタンはループ利尿薬等、他の利尿薬を使用していても体液貯留している患者に追加して使用される薬剤です。
バソプレシンV2受容体拮抗薬のトルバプタンは集合管のバソプレシンV2受容体に拮抗して、水(H2O)の再吸収をブロックします。水利尿薬とも言われ、電解質に影響を与えにくい利尿薬です。他の利尿薬と併用して使用します。また、入院下で開始する薬剤です。
トルバプタンも無尿の方には効果はありません。
トルバプタンが他の利尿薬と併用が必要な理由は作用機序的に単剤では利尿効果があまり期待できないからです。詳細はコチラをごらんください。
薬物動態情報
トルバプタンは尿中未変化体排泄率1%未満と肝代謝型の薬剤です。
また、血漿中遊離形率0.2%未満と蛋白結合依存型の薬剤です。
タンパク結合依存型の薬剤は、薬剤と結合する血中のタンパク質、主にアルブミンが変化するような状態(炎症、外科手術、腎障害など)では薬剤のタンパク結合率の低下(=薬剤の遊離形濃度の増加)の可能性があり、血中濃度が上昇する可能性があります。
血中濃度が上昇すると副作用発現(肝機能障害や血球減少)の可能性もありますので注意が必要です。
CYP3A4、P糖蛋白質(P-gp)の阻害作用を持つ薬剤との併用に注意が必要です。
副作用
急激な水利尿から脱水症状や高ナトリウム血症のリスクがあり注意が必要です。口渇はこれらに気付くサインになります。利尿薬の中でも特に口渇が発現しやすい薬剤で、水分制限が緩和されることがあります。口渇を感じにくい方や訴えることのできない方への投与は禁忌となるため要注意です。
“ループ利尿薬・トルバプタン薬物動態情報まとめ”のまとめ

- 短時間作用型ループ利尿薬:フロセミド
- 長時間作用型ループ利尿薬:トラセミド(抗アルドステロン作用あり)、アゾセミド(作用時間が一番長い)
- ループ利尿薬はアルブミンと結合した薬剤が作用を示すため、アルブミン→フロセミド静注の順で投与する
- 短時間作用型ループ利尿薬の長期投与は予後悪化の可能性
- ループ利尿薬の投与量が多いほど、心不全患者は死亡率のリスクが高い
- 低カリウム血症に注意
- ループ利尿薬等と併用が必要
- 脱水症状や高ナトリウム血症、肝機能障害に注意
- 口渇を感じにくい方や訴えることのできない方への投与は禁忌
- CYP3A4、P-gpの阻害作用を持つ薬剤との併用に注意
ループ利尿薬もトルバプタンも無尿の人に投与しても利尿効果はありません。
ループ利尿薬・トルバプタンの薬物動態情報や注意事項等を把握して、薬の適正使用につなげていきましょう。
- Masuyama T, et al, Superiority of long-acting to short-acting loop diuretics in the treatment of congestive heart failure, Circ J. 2012;76(4):833-42. doi: 10.1253/circj.cj-11-1500.
- Eshaghian S, et al, Relation of loop diuretic dose to mortality in advanced heart failure, Am J Cardiol. 2006 Jun 15;97(12):1759-64. doi: 10.1016/j.amjcard.2005.12.072.